(2021年3月9日)
EWI-SOLOが出た今、EWI5000の存在価値はグッと落ちたと言わざるを得ません。内蔵音源の音質もSOLOのほうがいいようですし。
5000はWindows Vistaのようなもので、失敗作だったのでしょう。とにかく動作が不安定で、ステージでは怖くて使えませんでした。
音色も安っぽく、プロはみんな4000Sに戻っていったようです。
しかし、記録として、以下、5000が発売された直後のリポートをそのまま残しておきます。
2014年7月末。待ちに待ったEWI5000が発売されました。
予約してあったので、31日に届きました。若干の期待と大きな不安を持って開封し、さっそく簡単なテストをしてみましたので、速報としてまとめておきます。
パッケージと初期設定
アマゾンで予約注文しましたが、剥き出しの箱で届きました。

中身は
- EWI5000本体
- ワイヤレスレシーバー
- USBケーブル1本
- USBパワーアダプター1つ
- ネックストラップ
- クリーニングクロス
- マニュアル類(すべて英語で日本語訳は一切なし)

このうち、使いものにならないな~と最初に思ったのはネックストラップです。
EWI4000Sに付属しているものより上質な、ワンタッチで長さ調整できるものを期待したのですが、クリップがチャチで固く、下手すると緩まなくなって首から外せなくなります。別に用意しないといけないでしょう。
マニュアル類はクイックスタート・ガイド(実質7ページ)と注意書き、エディターソフトのダウンロード指示書き。
説明書と呼べるのはクイックスタートガイドだけですが、日本語はなし。英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語のみ。日本はEWIユーザーが世界でいちばん多い国だと聞いていますが、完全無視。そのうち別冊で日本語版がつくのでしょうが、間に合わなかったようです。
最初にやるのはバッテリーを本体にセットすることですが、バッテリーカバーがプラスドライバーネジで固定されているため、ドライバーが必要です。EWI4000Sと違い、バッテリーを頻繁に交換することは考慮されておらず、無線電話機の子機バッテリーのような小さな端子で接続するため、予備バッテリーを持って切れたら交換する、というようなことは難しいでしょう。なにしろ端子があまりにも小さく、しかも奥まったところにあるため、細身のラジオペンチなどを使わないと抜き差しが厳しい。無理に指だけで抜き差しすると断線しそうです。こんな小さなコネクターで断線したら、修理も不可能に近いでしょう。
これがデジカメなどに使われる汎用の電池で、ワンタッチでパチンと装着できるようなら、常に予備電池を充電済みにしておき、早め早めで交換するということができるのに、残念です。
しかし、善意に解釈すれば、デジカメのように入れ替わりが激しい商品ではなく、EWIは長く使う使命を持つ楽器なのだから、電池も将来にわたって必ず入手可能なものにするために敢えてこういう形にしたのかもしれません。(それにしては交換電池の販売もまだのようですが)

充電はUSBケーブルで行います。AC電源にアダプターで直接つなぐか、パソコンのUSB端子につなぎっぱなしにするかです。充電しているときはケースにしまえないのが面倒です。
パソコンにつないだ場合はパソコンが切れていたり、充電不可のUSB端子ではダメなので、事実上はAC電源(コンセント)にアダプターでつなぐことになるはずです。
また、EWI-USBのように、パソコンにUSBでつなぐと音もパソコン経由で……というわけではないので、パソコンにUSBでつなぐのは完全な外部MIDIコントローラーとして使うときか、音色エディターを操作するときだけです。
充電しながらでも音声出力端子やワイヤレスから音は出ますが(マニュアルにもそう明記されている)、どうも充電しながらだと後述のプツプツ音切れする致命的な弱点が出やすくなるようなので、演奏するときは完全に外したほうがいいようです。
次にワイヤレスレシーバーのセットアップ。アンテナがマニュアルと一緒にビニール袋に入っているので取りだして組み立て、電源を入れます。
で、これもちょっと問題ありなのですが、ワイヤレスレシーバーにはバッテリーが内蔵されておらず、必ず電源につないでおく必要があります。この電源もUSB端子なので、実際にはAC電源(コンセント)につなぐことになりますが、ライブなどでレシーバー設置場所周辺に電源コンセントが余っていないときは面倒です。せっかくのワイヤレスなのだから、これはぜひともバッテリー内蔵にしてほしかったですね。
また、付属するAC電源アダプターは1つだけなので、ワイヤレスレシーバーをセットしているときはEWI5000の充電用には使えなくなります。同時に使うことはない、ということでしょうが、いちいち外して付け替えるのが面倒なら、AC電源アダプターは2つほしくなります。iPadなどの付属物としてもついてくるので、持っている人は多いと思いますが。
……と、操作性の面でいろいろ書きましたが、このワイヤレス装置の性能自体はすばらしくて、タイムレイテンシー(送受信における発音の遅れ)や音質劣化はほとんど気になりませんでした。
音を出してみる
さっそく音を出してみました。
実は、発表されていた音色一覧表を見たときには少なからずショックを受けました。
いちばんほしかった(というか、私にとってはこれだけでもいい、というほどマストである)ViorinやCelloなどの擦弦楽器リアルPCM音源が一切入っておらず、その代わりに絶対に使わないであろうシンセサイザー系やラッパ隊セクションなどがごちゃごちゃと入っていたからです。
発表会でのデモ演奏動画を見ても、なんか安っぽい音だし、これはあまり期待できそうもないなあと、半ば諦めていたのですが、その通りの内容でした。
↑音色番号00番でさっそく音出しテスト
それでも00番~07番までのサックス系音源は、それなりにまとまっている感じではあります。
EWI4000Sでは出せなかった生サックスの感じが出ている分、「サックスシミュレート」感や、いかにもデジタル音源でございます的なデジデジした質感が目立ち、EWIという独自の楽器としての立ち位置というか、EWIとしての「尊厳」、艶めかしさのようなものが失われて淡泊になった感じでしょうか。
EWI4000Sは、デジタル音源ではあってもアナログシンセサイザーを模していて、それなりのEWIらしさがありました。でも、EWI5000は、なんか、EWIのボディにCASIOの子供向けデジタルシンセサイザーの中身を入れてしまったような感じなのですね。
CASIOのホームユース志向のシンセサイザーを悪く言っているわけではありません。あれはあれで大したものです。コストパフォーマンスが。でも、プロがシンセサイザーを選ぶ場合、わざわざあれは選ばないでしょう。シンセサイザーといえども、ローランドの音とかコルグの音、YAMAHAの音といったものがあって、それぞれの個性を気に入って選ぶわけです。
EWI5000の音は、そうした個性、EWIとしてのアイデンティティのようなものがあまり感じられないのです。スッキリしすぎていて、薄味。これとこれとこれ、100個入れました。やったね! ……というノリ。
もっと嫌みっぽく言えば、管楽器や弦楽器のプレイヤーではなく、DJサウンドやラッパーが作りましたというノリ。
あるいはプレステのようなゲーム機を設計しているようなノリ。
音源制作のポリシーというか職人魂のようなものが見えてこないのです。GullitanやMOTUの音源にはそういうものが感じられるのですが、EWI5000の音源はかなりそっけない印象です。
音色の印象だけでなく、EWI4000Sに比べると、演奏しているときの一体感というか、リニアなレスポンス感が若干落ちます。EWI4000Sは粘りのある演奏感で、微妙な息の強弱やベンド奏法にきれいに(曲線的に)反応してくれますが、EWI5000は反応が直線的で、リコーダーを吹いているような単調さを感じます。
また、ちょっと戸惑うのは、アルト、テナー、バリトン、ソプラノ……の順に入っていますが、7オクターブという広域にわたって音色作りをしなければいけないため、ホームポジション(オクターブキーの真ん中を押さえている状態)では、ソプラノはソプラノの音域よりずっと低い音が出るということです。ソプラノらしい音を出すためにはオクターブキーでオクターブ持ち上げて吹く必要があります。そのまま吹くと、むしろソプラノサックスがアルトサックスより低い音色で鳴ったりします。
音色を切り替えて同じポジションで吹いたとき、テナーの音がソプラノに変わる、アルトに変わる、バリトンに変わる、という感じにはなりません。ソプラノはこの音域ポジション、アルトはこの音域……と、覚えておく必要があります。
考え方によってはこれはこれで理にかなっているのかもしれませんが……。
↑ソプラノサックス2の音色だが、オクターブキー中央位置で吹くとかなり低い音で、最初は戸惑う
↑超高音域、超低音域はどの音色でもほぼ同じ印象に(シンセサイザーっぽく)なる
それと、吹き口のバイト(噛む)センサーがEWI4000Sに比べるとかなり反応の仕方が変わった感じです。
EWI4000Sはちょっと振動を加えるだけでも音に揺れが出たのですが、EWI5000ではしっかり噛まないと変化しません。センサー感度を上げてもEWI4000Sほど敏感にはなりませんでした。
最大の困惑……音が切れる!
……で、そんなことよりなによりも、想定外のショックだったのは「音が切れてしまう」ということです。
最初は「まさか?」と耳を疑いました。
音楽録音ソフトでガンガン編集しているときなど、CPUの処理やメモリが足りなくなって音がプツプツ切れたり、デジタルノイズが入ったりすることは、打ち込みをやっている人間なら誰もが経験していることですが、まったく同じような感じで、時折音がプツプツと切れてしまうのです。
ワイヤレスでもワイヤードでも同じなので、無線の関係ではありません。
工場出荷時状態でそうなるので、調整不良でもありません。
↑届いてすぐ、工場出荷時のままテストしているときからすでに音切れ現象が発生
上の動画は、EWI5000が届いたその日に、とりあえずの状態でテストしているときのものです。
11秒のところでまず短く音切れして、32秒あたりで誰もが分かるようなひどい音切れが生じています。
また、工場出荷時の状態ですと、ブレスセンサーの感度が粗すぎて、息を細くしていってフェイドアウトさせようとすると、最後のほうでプッと音が途切れてしまいます。
17秒~22秒あたりの現象がそれです。
もっとなだらかにす~~っと消えさせたいのに、あるポイントからプスッと消えてしまいます。
なんとかこの現象を回避できないかと、その夜はブレスセンサーの調整などをずいぶんやってみました。ある程度はよくなる感じですが、完全には回避できませんでした。
ちなみに最初の動画(音色00番での試奏)はセンサーなどを調整した後です。
この音切れ現象はブレスセンサー調整にかなり関係しているらしいことは分かったのですが、感度を甘くすると音切れがなくなるというような単純なものでもなく、なんとも微妙です。
今のところ、届いた直後よりはかなりマシになった感じですが、それでもときどきプツプツと音切れしてがっくりきます。
音色にも大きく関係しているようで、00~07あたりはかなり調整されているのか、出にくく、10番(ハーモニカ)や19番(ポップブラスセクション)などでは出やすい、といった印象があります。
頻繁に出るのなら「これはちょっとないでしょ」とクレームで送り返したくなりますが、忘れた頃にプツッとくるので、ますます苛立たせられます。
多分、「初期不良」などの故障ではなく、設計が甘いのでしょう。
100個も音色を入れる必要はなかったのに頑張りすぎてしまい、そのくせ、値段を抑えるためにCPUやメモリをぎりぎりにケチった結果ではないでしょうか。
願わくば、早急にファームウェアアップデートなどで安定性を増してほしいものです。
↑ブレスセンサーなどを調整後。これでもだいぶよくなった。初日、未調整のときはもっと頻繁にプチプチ音切れが出ていた
音色エディターの出来と調整可能性

音色エディットソフトはEWI4000Sについてきたやつがひどすぎた(環境によっては動かなかったりした)ので、それに比べればOKです。しかし、あまりいじれないですね。ちょっとでもいじると極端に音が崩れてしまいます。リバーブやディレイなどが中心になるでしょうか。特にレゾナンスはちょっとでも上げるとたちまちキンキンしたシンセサイザー的な音になってしまう感じです。
ただ、EWI5000の内蔵音源で力を入れている吹奏楽器シミュレート(特に最初の00~07あたりのサックス系シミュレート音源)は、そのままだととってもしょぼく聞こえてしまい「やっぱり本物のサックスにはかなわないな」という評価で終わってしまいがちなので、エディットするなら大きく変更して、シンセっぽい音にしたほうがライブでは「聴き映え」するようにも思います。
そう気がついてからは、私はライブ用に00~07番は、本物のサックスらしさを完全に捨て、EWIとしてどれだけアピールできる音色になるかを主眼にしてエディットするようにしました。ディレイを短めにしてフィードバックをあまりさせず、ディレイのヴォリュームは上げて音を太くするとか、リバーブを派手にかけるとか、レゾナンスなどをいじって派手目にするとか……。
音切れ現象の出やすさ、出にくさとエディットがどの程度関係しているのかはまだよく分かりません。
ものすごく微妙で、長時間吹いているうちに安定してくるような気もします。(製品として「慣らし」が必要? デジタルなのに??)
ちなみに、
製品発表会で宮崎隆睦氏が語っていたという「音色エディットで若干アタックを遅らせ、荒っぽさを出したい時はタンギングで出すようにすれば、コントロールしやすくなる」というのは、もしかすると、音色エディットでアタックを若干遅らせれば音切れしにくくなる、という意味なのだろうか? と勘ぐってみたりもしました。
というわけで、これを書いているのはEWI5000が発売されてすぐ、届いて翌日の印象をまとめているわけですが、現時点では音飛びが怖くてライブで使うのはかなり難しいかな~というところです。
プチっというデジタルノイズや音飛びは、電子楽器奏者としては、単純なミストーンや演奏ミスよりずっと恥ずかしいことです。ただでさえデジタルはチャチだよね、本物にはかなわないよね、という評価を受けながら、敢えてEWIを演奏するわけですから、一瞬の「プチ」で、「ああ、やっぱりね」と貶まれてしまうのです。
昨日、最初に吹いた時点では「これは全然使えないじゃん」という印象でしたが、調整後、また、USBケーブルを外して吹いたほうが安定するようだということが分かり、今は、ラフなライブなら使えるかなという感じにまで気持ちが持ち直してます。
いきなり辛口で書きましたが、いいところもあるのです。
まずはなんと言っても無線内蔵。これはほんとに助かります。レシーバーがバッテリー内蔵式だと完璧でしたが、性能的には無線に関しては文句ありません。
次に本体そのもの(筐体)が改善されたこと。
裏のオクターブローラーはEWI4000Sのようにコロコロいつまでも回転することなく、少し安定しました。これでほんのちょっと指を緩めただけでミストーンが一瞬出るようなことが減りました。
わずかですが重量が減ったのも大変嬉しいことです。数十gですが、持った感じが全然違います。やはりEWI4000Sは重すぎました。
今後への期待と不安
私自身の音楽制作においては、今後もEWI-USBに付属していたAriaのViorin(TH)をもっぱら使うことになるでしょう。
 ↑AriaのViorin音源での演奏サンプル 『Another Christmas』(Jin Soda) (クリックでMP3再生)
↑AriaのViorin音源での演奏サンプル 『Another Christmas』(Jin Soda) (クリックでMP3再生)
……曲の最後の部分、Ariaのヴァイオリン音源の中音域と低音域(チェロに見立てている)での絡み合い
その際、EWI-USBはMIDI入力機として不安定(すぐに右下のタッチセンサーが無反応になるなど)なので、今までは重いEWI4000SにぶっといMIDIケーブルをつないでやっていましたが、今後はEWI5000をUSB接続して演奏することになるでしょう。(まだやってみていませんが)
しかし、MIDI入力機としてだけのためにEWI5000を使うというのではあまりにも悲しすぎます。
そのために、明日からも調整に挑むことになるでしょう。
内蔵音源を変える気がないなら、とにかくファームウェアバージョンアップで、一刻も早く安定性を増してほしいです。せっかく高性能な無線内蔵なのですから、ライブで安心して吹きまくりたいですしね。
それでもどうしてもしっくりこなければ、ライブではEWI4000Sを使い続けることになるかもしれません。
いっそ、もし内部のメモリがフラッシュメモリなどであれば、内蔵音源そのものを入れ替えられないものでしょうか。
いろんな音源セットをネットでダウンロード販売し、それをパッチとして入れ替えすることで擦弦楽器シミュレートのEWIや尺八・フルート系のEWIなどなど、音数を絞って、音質を極限まで追求したプロ志向のEWIビジネスを展開してもらいたいと切に願います。
まずは擦弦楽器セットを! 2万円くらいであれば飛ぶように売れるのでは?
前から言っているように、私はAriaのViolin(TH)音源のクオリティの擦弦楽器音源が内蔵されたEWIが出れば、20万円でも買うつもりなのですから。
それを受け入れるギアとしてのEWI5000になりうるのであれば、9万円は全然高くありません。安いと言えるでしょう。
歴史に名を残す楽器となる可能性もあります。
しかし、今のままで終わるなら、中途半端な失敗作として忘れられる運命の楽器になってしまうかもしれません。
私はEWI5000が今のままで変わらないとしても、まだまだつき合うつもりですし、与えられた内容でできうる音楽を作る覚悟ですが(↓)、これだけ可能性を秘めたハードウェアなのですから、ぜひともソフトウェア部分を煮詰め直して、新たな音楽を創造する道具として高みを目指してほしいものです。

『Digital Wabi-Sabi ─As Easy As EWI』 iTunesストアで発売中↑Click
(または、iTunesを開いて「jin soda」で検索!)


アマゾンMP3でも発売中!↑ こちらは高音質のMP3ファイルで900円!


(2014年8月17日追記)
昨日(8月16日)、EWI5000を使って(MIDI出力のみで)録音中、なんの前触れもなく突然、電源が入らなくなりました。
バッテリーを抜き差ししてみてもダメ。
電源が入らないため、リセットもできません。
USBをつなぐとUSBからの電気は受け取るようですが、LEDが全部表示(88)点滅をするだけで操作不能。
やむなく、購入したアマゾンで返品・交換手続きをしたところです。
思うに、本体よりも電池(専用のリチウム充電池)が怪しいような……。
4000Sのように単三電池だったりすれば電池交換で簡単に確認できますが、EWI5000の電池は専用?のもので、まだ予備バッテリーも販売されていないようですので確認できません。
Twitterでも、やはり音が途切れる現象を報告しているユーザーがいました。
どうもいろいろとチェックが甘いまま製造・出荷しているような気もします。
私だけのレアケースであればよいのですが……。
それにしても、ネット上の書き込みを見ていると、EWIを愛している人たちが少なくないことがよく分かります。また、EWIファンがEWI5000をいかに待ち焦がれていたか、も。
それだけに、高くてもいいから、志のある設計、しっかりした品質で出してほしいものです。
ウィンドシンセサイザーという楽器、最後の砦なのですから。
(2014年8月18日追記)
本日、交換品がアマゾンから届きました。16日の夜にアマゾンのWEBサイト上で返品・交換の手続きをし、30時間後にはもう届くのですから、アマゾンはやはり大したものです。
で、今度のは、最初のもののようにいきなり音がプツプツ途切れるようなことはありませんでした。まったくないというわけではなく、「○○セクション」と名づけられている音色(Pop Brass Section や Woodwinds Sectionなどなど)ではたまにプツッときましたが、頻度は最初の製品よりずっと少なく、これなら許容限度内でしょうか。
音色切り替えのときに読み込みに時間がかかるのはメモリ量が多い音色なのだと思いますが、そういう音色で出やすいようです。ということはやはりCPU性能に余裕がないということなのでしょう。
しかし、最初に届いた製品と、音そのものが違うようです。安定しているせいか、ズンっと太く、かつクリアに聞こえます。
プラシーボ効果ではないと思うので、やはり最初のは不良品だった可能性が高いです。
音の印象が違うのはなぜなのでしょうか。CPU性能が1ランク上がったかのような印象です(そんなことはありえないはずですが)。
で、何日もかけてやっていた音色EDITを一からやりなおしました。
不思議なことに、この音色エディットも最初の製品のときより安定しているし(最初の製品ではパラメータをいじるたびにブツブツとノイズが入ったり音が切れたりしていましたが、そういうこともあまりなくなりました)、パラメータの調整による音の変化の仕方も違っているような気がします。気のせいかもしれませんが……。
基本的には、エフェクトセクションでDelayを短く(時間もFeedbackも短く)、かつVolumeは大きくかけることで音色を太くし、ライブ用にはリバーブのないアンプにつなぐことを前提にして、最初からリバーブを派手目にかける、あとはAttackをほんの気持ち遅らせたり、音色によってはレゾナンスで派手目にしたり、ブレスで音程が微妙に変化するようにしたり……といった調整です。
サックス系の音色は生サックスにかなり近いので、出音のバリっとしたざらつきを残しつつ、後ろは太く派手に……という感じでやっていくと、ライブでもそれなりに色気が出そうです。
しかしまあ、早めに分かりやすく壊れてくれてよかったです(突然、電源が入らなくなるという分かりやすい故障)。
交換品が出音の印象まで違っているということを考え合わせると、どうやらバッテリー単体の不良ではなく、本体の電子回路、CPU回りとかが不良だったのだと思います。いわゆる初期ロット不具合の人柱になったのか……。
あるいは電子部品の品質が不安定で、製品ごとにかなりばらつきがあるのかもしれません。
(2021年3月9日 追記)
2020年秋にEWI-SOLOが出たことにより、5000の存在価値は完全に消えたかなと思います。
私の5000は今や完全にMIDI入力機に成り下がっており、EWI-SOLOを入手した後は手放そうと思っています。
 次(EWI4000S、5000、Aria音源の吹き比べ) へ
次(EWI4000S、5000、Aria音源の吹き比べ) へ
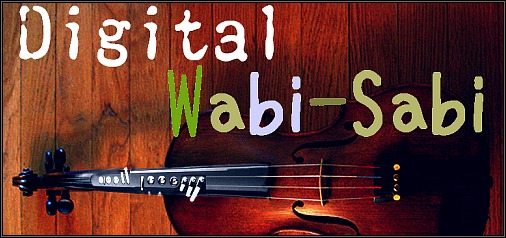
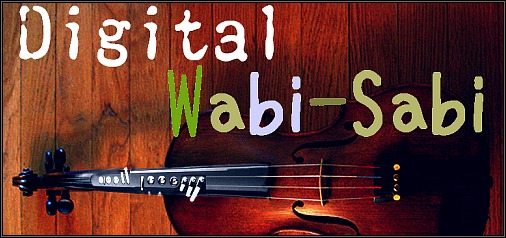






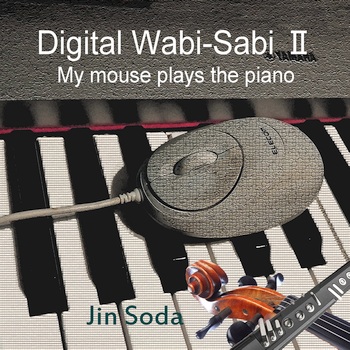
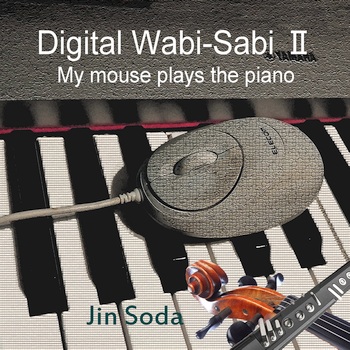
 (takuki.com のHOMEへ)
(takuki.com のHOMEへ)